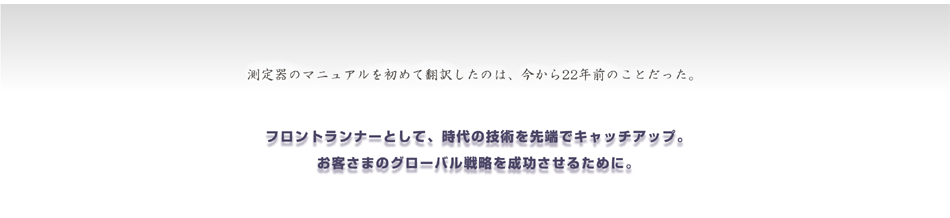信号解析に関する翻訳で、residual FM(残留FM)という言葉が出てくる(例えば、PXA Xシリーズ シグナル・アナライザ、マルチタッチ N9030Bのp4)。
residual FM(残留FM)は、無線機やスペクトラム・アナライザの局部発振器の位相雑音の大きさを表わす指標の1つである。位相雑音の大きさを表わす指標には、SSB位相雑音、残留FM、残留φMがあり、いずれも周波数領域で定義される指標である
理想的な局部発振器の出力は、理想的な正弦波として、
V(t)=Acosωt、ω=2πf
と表される。しかし、現実には、熱雑音などのランダム雑音により、振幅Aと位相ωtがランダムに変動している。これらの変動分をΔA(t)、Δφ(t)とすると、現実の局部発振器の出力は、
V(t)=(A+ΔA(t))cos(ωt+Δφ(t))
と書ける(ΔA(t)は振幅雑音、Δφ(t)は位相雑音)。
しかし、測定が容易な物理量は、発振器の出力(基本波)近傍での、位相変動に起因する雑音パワー(雑音側波帯)なので、間接的な位相雑音の定義として、基本波からのオフセット周波数における、1Hz帯域幅当たりの片側(Single Side Band)の雑音パワーと発振器の全パワーとの比をとり、SSB位相雑音[dBc/Hz]で表わすのが一般的である。このSSB位相雑音を、基本波からのオフセット周波数fの関数としてL(f)と書くと、残留φM(ΔΦ(f))のRMS値の2乗(Δφ_rms^2)は、L(f)を、ベースバンド信号(ここではランダム雑音)の下限周波数と上限周波数に対応するオフセット周波数の間で積分したものとして、
Δφ_rms^2=2∫L(f)df (1)
で定義される。
また、瞬時周波数f(t)と瞬時位相(角)φ(t)の間には、ω(t)=2πf(t)=dφ(t)/dtの関係があるので、周波数の微小変動Δf(t)と位相の微小変動Δφ(t)の間に、
Δf(t)=(1/2π)(dΔφ(t)/dt)
の関係が成り立つ。この式の両辺をフーリエ変換すると、フーリエ変換の性質(dΔφ(t)/dt⇔iωΔφ(ω))から、
Δf(f)=(2πfi/2π)Δφ(f)
なので、残留FM(Δf(f))のRMS値の2乗(Δf_rms^2)は、
Δf_rms^2=f^2Δφ_rms^2=2∫f^2L(f)df、(1)式から
となり、SSB位相雑音L(f)に基づいて定義できる。
残留FMについては以下を参照。
Design Principles and Test Methods for Low Phase Noise RF and Microwave Sources(英語PDF)のp2からp7