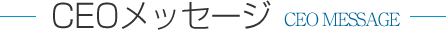西アフリカで2年半ほど滞在していた20代のころ、マラリヤを患ったことが2度あった。その後10年ほどは毎年、マラリアに罹った時期になると、身体がその時の悪寒や脱力感を想起するのか原因不明の発熱に悩まされ続けた。
最初のマラリヤは突然やってきた。ある日、朝起きると身体中が熱っぽかった。体温を測ると41度。
「これぐらいは…」と勤務先の大使館へと向かった。その日の朝は、パウチ(外交行嚢=外交文書)を空港で引き取らなければならなかったため、休むわけにもいかなかった。
ふらつきながらも早朝のルーティン業務をこなし、現地スタッフのピーターと2人で空港へと向かった。車中、ピーターが、わたしの顔を見て声をつまらせた。
「Mr.スナガワ、熱があるのでは?マラリヤなら死ぬことも…」
「アフリカは暑いからネ。ありがとう」
と気丈なふりをしたものの、意識はうつろだった。
無事に行嚢を受け取り帰館すると、ピーターの姿が見えなくなった。
わたしは届いた文書を急いで整理し、上司の参事官室へ携行した。
「パウチが届きました」と開けっ放しの入り口からペコリと部屋に入ると、ピーターが参事官の傍に立っていた。
「バカヤロー!ピーターが教えてくれた」
「何度だ!朝測ってきたんだろ!」
「はっ、いえ…」と濁すわたしに
「体温は!」と畳みかけてきた。
「大したことは…40度…いや、もう下がっていると」
「バカヤロー!病院へ行け!運転はジローにさせろ。今すぐ行け」と怒鳴った。
「はっ、でも、報告書を書いてからでも…」
「お前はバカか!救いようがないな!これは命令だ!すぐ行け!」
上司の剣幕に圧倒され、街中の小さな病院へと向かった(当時、市内にはイギリス人医師が開業している小さな診療所が1軒あった)。車中、運転手のジローがぽつり。
「これで、Mr.スナガワもアフリカ人」
診察の結果、やはりマラリヤに罹っていた。治療薬はないため、予防薬をもらって大使館に戻った。
「薬をもらってきました」と参事官に報告すると
「バカヤロー、さっさと帰れ!」とまたしても。
「はっ、もう大丈夫です。ありがとうございます」と元気を装うわたしに、
「報告書を書いたらすぐに帰れ。ただし明日は休め。明朝の援助貨物の確認は俺一人で行く。これは命令だ。いいな!」と口調を強めた。
翌朝は、日本の援助物資が港へ荷下ろしされる予定であったため、その確認に参事官のお供をして立ち会うことになっていた。
翌朝…
いつものように早朝のルーティン業務をこなし、現地スタッフとロビーで打ち合わせをしながら参事官の出勤を待っていると、玄関前の車寄せに到着した車中から参事官が出てきた。わたしを見つけるなり、
「バカヤロー!休めと言っただろう!今日は何度だ!」
「40度はありません…」
「バカヤロー!大丈夫か…。無理するな!お前一人の命じゃないぞ!…大切にしろ!」と眼差しは優しげだった。
「少し待ってろ。準備は出来ているのか」
そう言うと参事官は部屋に一旦入り、ほどなくして出てきた。
手に持っていたカバンと水筒をわたしに手渡し、
「じゃ、行くか。家内が水を用意してくれた。それでも飲んで…」と車寄せまで先に歩き出した(当時、同国の公共インフラは壊滅し電気は供給されず、飲み水も満足に手に入らない状況にあった)。
「ありがとうございます」と後を追った。カバン持ちとして。
━━━
あれから、四半世紀が経つ。わたしが彼に仕えたのは、西アフリカでの2年ほどであったが、事あるごとに「バカヤロー」とわたしを怒鳴りつけながらもわたしを見守ってくれたその上司は、もうこの世にはいない。その後、わたしはアフリカから中東へと転勤となり、彼は功績が認められさらなる階段を上っていくこととなった。彼の働きにより、日本は同国への最大の援助国となったのである。
彼は晩年、外務省を辞めたわたしの生き方をいつも気にしていたと彼の家族から話を聞いた。彼の火葬の日、遺骨を拾わせていただいた帰りの車中から見えた風に舞う満開の桜の花びらに涙が止まらなかった。その彼は、わたしに誠の外交官のあるべき姿勢、人の生き方を教えてくれた最も尊敬できる偉大な師であり、戦後を生きた日本の誇りある人間外交官であった。わたしのその後の生き方の選択を真の意味で見抜いていたのは、外務省の中で彼ただ一人だったかもしれない。
「バカヤロー、お前一人の命じゃないぞ!」