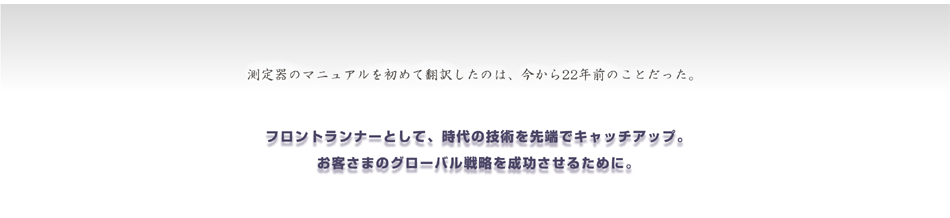半導体デバイス測定に関する翻訳で、Vthという言葉がよく出てくる(例えば、B1500A半導体デバイス・アナライザのp3)。Vthは、Voltage THreshold(しきい値電圧)の略である。
CPUやメモリなどのLSIには、MOS(Metal-Oxide-Semiconductor、金属酸化膜半導体)構造のトランジスタ(MOSFET、FETはField Effect Transistor(電界効果トランジスタ)の略)がスイッチング素子として使われている。MOSFETのゲートに電圧(電界)を印加する/しないによる、ソース-ドレイン間の電流のオン/オフ制御(スイッチ)を利用して、論理回路が形成されている。
nチャネル(n型)MOSFETは、p型半導体基板上にチャネル(電気の通り道)と呼ばれる領域を挟んで離れた2箇所にn型半導体領域(一方にソース電極、もう一方にドレイン電極が接続される)がある。チャネル領域の真上には酸化膜(絶縁層)を挟んで金属電極(ゲート電極)が存在する。
ゲート電極に少しずつ正の電圧を印加していくと、絶縁層を挟んだp型半導体基板の多数キャリア(電流の担い手であるホール)が正の電圧に反発してグランドに逃げて、動けないマイナスの電荷が残り、空乏層が形成される(ゲート電圧に応じて空乏層が厚くなっていく)。この状態では、ゲート直下には、動けないマイナスの電荷が残っている空乏層があるだけなので、ドレインに電圧を印加してもソース-ドレイン間に電流は流れない。
さらにゲート電圧を大きくしていくと、空乏層の厚さだけでは対応できなくなり、ソースとドレインのキャリア(電子)がゲート直下に引き寄せられて、ゲート直下のp型半導体が電子の多いn型半導体に反転する(反転層が形成される)。反転層が形成されると、ソースとドレインがn型半導体でつながるので、電流が流れ始める。このときのゲート電圧をしきい値電圧(Vth)と呼ぶ。
MOSFETについては、以下を参照
山形大学大学院理工学研究科廣瀬文研究室 > 半導体デバイス教科書プロジェクト > 第6章 MOSFET
Vthについては、以下を参照。