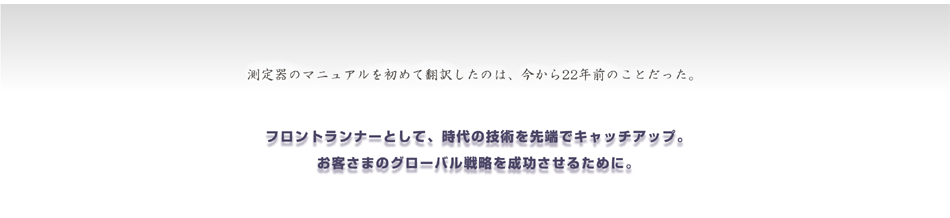電子デバイス測定に関する翻訳で、CNTという言葉が出てくる(例えば、プレシジョン電流/電圧アナライザシリーズのp4)。
CNTは、Carbon Nano Tube(カーボン・ナノ・チューブ)の略である。炭素(カーボン)原子のみでできた結晶性物質としては、ダイヤモンドとグラファイト(黒鉛、鉛筆の芯として用いられている)がよく知られている。
炭素原子には、結合の手(価電子)が4つあり、ダイヤモンドの結晶構造は、正四面体の中心に位置する炭素原子の4つの結合の手が、正四面体の4つの頂点に位置する炭素原子の4つの結合の手の内の1つと結んで結合している(最近接の炭素原子と価電子を1つづつ共有して、閉殻構造になる(オクテット則を満たす)ことにより最も安定した状態になっている)。正四面体の4つの頂点に位置する炭素原子の残りの結合の手も、同様に最近接の炭素原子の結合の手と結ばれ、3次元に広がる結晶構造を形成している。4つすべての価電子が共有結合に用いられるので、ダイヤモンドは非常に固く電気を通さない。
一方、グラファイトは、炭素原子の4つの価電子の内の3つだけがそれぞれ平面上で隣接する3つの炭素原子と共有結合して、平面正六角形(6員環)構造の結晶を形成している。余った電子は平面内を自由に動き回れるので、グラファイトは電気をよく通し、平面構造の間(層間)はファンデルワールス力による弱い結合なので、剥がれやすく鉛筆の芯に使用されている。
カーボン・ナノ・チューブは、平面構造の一層のグラファイト(グラフェンと呼ばれる)を円筒形に丸めたものである。丸めたときのねじれ方により、バンド構造(結晶を構成する原子の周期的な配列の仕方により、電子軌道のエネルギー準位が、電子が完全に詰まっている価電子帯、電子が存在可能な伝導帯、価電子帯と伝導帯の間のバンドギャップと呼ばれる電子の存在できない禁制帯に別れることで、金属は伝導帯に電子が存在して電気が流れやすく、半導体は伝導帯に電子が存在しないがバンドギャップが小さいので熱励起などにより価電子帯の電子が伝導帯に遷移して少し電気が流れ、絶縁体は半導体と同じだがバンドギャップが大きいので電気が流れない。)が変化し、金属にも半導体にもなる。
カーボン・ナノ・チューブは、その構造から、化学的に安定で、温度に対する安定性が高く、軽量(アルミの約半分の重さ)で、電流密度が高く(銅の約100倍)、熱伝導性も銅の約10倍という特性を持っている。このような特性から、さまざまな用途が考えられ、半導体材料やLSIの金属配線材料としての研究開発も進められている。カーボン・ナノ・チューブを用いた宇宙エレベーター構想というのもある。
カーボン・ナノ・チューブについては、以下を参照