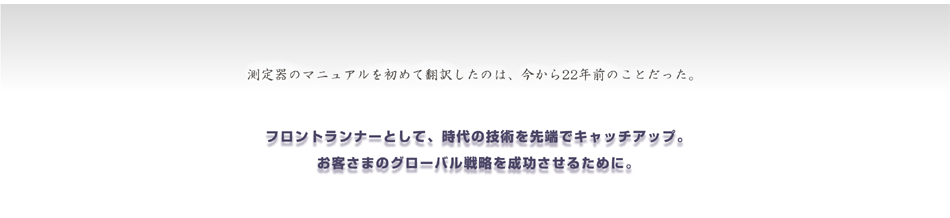ワイヤレス給電の測定に関する翻訳に、A4WPという言葉が出てくる(例えば、オシロスコープによるA4WP(Alliance for Wireless Power)測定(パート1))。
電気製品を動かすためには、電力を供給する必要がある。通常、AC100Vのコンセントに電源ケーブル(電気を通すワイヤ)をつないで外部電源から電力を供給する(充電池を使用する場合も充電のために、外部電源にケーブルをつないで電力を供給する必要がある)。これに対して、ケーブル(ワイヤ)を使用しないで非接触で電力を伝送することをワイヤレス給電と呼ぶ(非接触給電、非接触電力伝送、ワイヤレス電力伝送とも呼ばれる)。1995年にソニーのICカードのFeliCaで実用化され、2000年以降、コードレス電話の子機、シェーバー、電動歯ブラシの充電用などで実用化されてきた。ワイヤレス給電には、給電のためにワイヤをつなぐための電極の露出がないので水などによる腐食が起こり難い、製品を密閉状態にできるので故障が起こり難いといった利点があり、製品開発の自由度や安全性が向上する。
ワイヤレス給電方式は、放射型(電磁波の遠方界(エネルギーが伝搬する領域)を利用する方式)と非放射型(電磁波の近傍界(エネルギーが蓄積される領域)を利用する方式)に大きく分けられる。放射型には、マイクロ波を使用して大規模宇宙太陽光発電所から地上に電力を伝送する構想がある。非放射型は、磁界結合方式(変圧器などで、1次(送電)側のコイルと2次(受電)側のコイルがつながっていなくても、電磁誘導により交流が流れることを利用)と電界結合方式(送電側と受電側がコンデンサ(絶縁層を挟んだ電極)で隔てれれていても交流が流れることを利用)に大きく分けられる。磁界結合方式は、電磁誘導型(通常の変圧器(密結合トランス)と同じ原理を利用したもので、送電側のコイルと受電側のコイルを接触するくらいに近づける必要がある)と磁界共振型(液晶ディスプレイのバックライトとしてLEDが普及する前に使用されていた冷陰極管を点灯させるために用いられる調相結合トランス(磁気漏れトランス、疎結合トランス、高周波共振変圧器とも呼ばれる)の原理と言われている。例えば、ここを参照)に分けられる。
電磁誘導型には、世界で200社以上が加盟しているWPC(Wireless Power Consortium)が推進しているQiという規格(日本で最も普及している)とIEEEやスターバックス、googleが加盟していることが特徴のPMA(Power Matters Alliance)が推進しているPowermatという規格がある。磁界共振型には、サムスンとクアルコムを中心に誕生したA4WP(Alliance for Wireless Power)が推進するRezenceという規格があった。PMAとA4WPは、2015年に統合され、AirFuel Allianceという団体になり、AirFuel Inductive(電磁誘導型)とAirFuel Resonant(磁界共振型)の2つの規格を推進している。
ワイヤレス給電については、以下を参照。