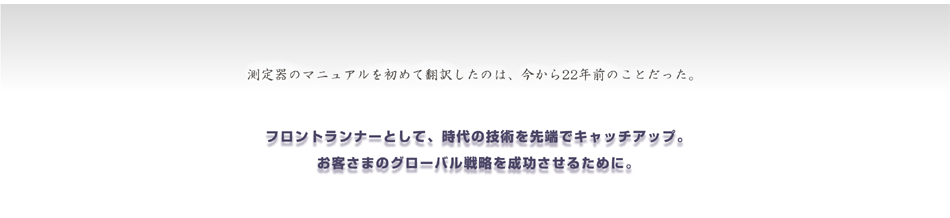波形発生器に関する翻訳に、direct digital synthesis(ダイレクト・デジタル・シンセシス)という言葉がよく出てくる(例えば、33500Bシリーズ波形発生器)。direct digital synthesis(ダイレクト・デジタル・シンセシス)は、略してDDSと呼ばれる。
DDSは、基準クロックから、直接デジタル的に、周波数が可変の任意の波形を発生させる方式である。PLLと1/n分周器を用いた間接的な発生方式に対するものとして、ダイレクト・デジタル・シンセシスと呼ばれる。
DDSは、加算器とラッチ(レジスタ)を組み合わせた累積加算器(積算器、アキュムレータ)、1サイクルの波形データが記録されているROM、デジタル信号をアナログ信号に変換するD/Aコンバーターから構成されている。
正弦波を出力するDDSでは、ROMには、先頭アドレスから最終アドレスまでのアドレスビット幅に、正弦波の位相ゼロに対応する振幅値から正弦波の位相2πに対応する振幅値が書き込まれている。アキュムレータは、基準クロックに同期して積算設定ステップで積算していく(積算設定ステップが1の場合は積算値は0、1、2、・・・、積算設定ステップが2の場合は積算値は0、2、4、・・・などとなる)。この積算値がROMのアドレスになり、このROMのアドレスの振幅値がD/Aコンバーターに送られ、アナログ出力となる。これは、積算設定ステップをn、ROMのアドレスビット幅をmビット、基準クロックの周波数をf_referenceとすると、DDSのアナログ出力の周波数f_outが、
f_out=(n/2^m)×f_reference
となることを表している。nを変化させると、瞬時に出力周波数が変化し、位相連続な波形を容易に発生できる。また、ROMに正弦波以外の任意の波形を1サイクル分書き込んでおけば、任意の周波数の任意の波形を発生でき、PLLと1/n分周器を用いた方式に比べて、回路が簡単で安価である。
ダイレクト・デジタル・シンセシスについては以下を参照。