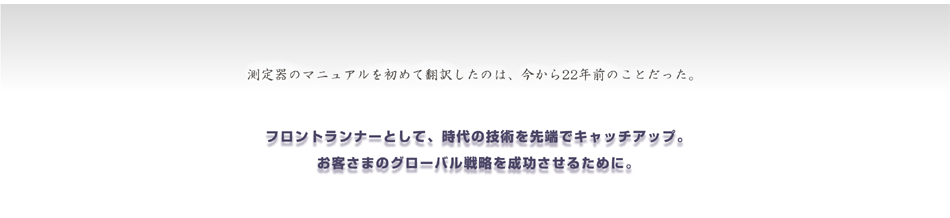無線通信測定に関する翻訳で、channel sounding(チャネルサウンディング)という言葉がよく出てくる(例えば、5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)の測定手法)。
channel sounding(チャネルサウンディング)のチャネルとは、無線通信における送信機と受信機の間の電波の伝搬経路のことで、サウンディングは「聞こえ方」から転じて「電波の伝わり方(伝搬特性)」という意味である。通常、チャネルサウンディングは電波伝搬経路の特性を評価(推定)するという意味で使用される。
特に、携帯電話などの移動無線通信システムでは、電波の経路損失、反射、吸収、回折、マルチパス効果、移動体の速度によるドップラー効果などにより、周波数、時間、受信位置に依存して電波の受信強度が激しく変動するフェージングが発生する。これにより、信号品質が著しく低下するので、デジタル・ビームフォーミング(MIMOやアレイ・アンテナの使用)を行って信号品質を確保している。これを行なうためには、電波の伝搬路の特性を測定(推定)すること(チャネルサウンディング)が必須となる。
最も簡単なチャネルサウンディングの推定は、伝搬路のインパルス応答h(t)を測定すること(伝達関数H(ω)を求めること)である。インパルス応答には、伝搬路のすべての情報が含まれていて、送信機から時間領域の任意の送信信号x(t)が送信され、インパルス応答がh(t)の伝搬路を通って、受信機でy(t)という信号が受信されたとすると、、y(t)は畳み込み積分を用いて、
y(t)=∫h(τ)x(t-τ)dτ=h(t)※x(t)、※は畳み込み積分を表わす記号 (1)
のように表され、伝搬路の特性が推定されたことになる。
しかし、インパルス応答を正確に測定するには、周波数帯域幅の広い理想的なインパルスを使用する必要があるが、帯域幅を広くすると測定帯域全体でのS/N比が低下したり、帯域幅が制限される移動無線通信には不向きである。このため、インパルス列を用いて平均してS/N比を上げたり、チャープ信号を用いたりする方法がある。
また、自己相関関数がδ関数となるようなホワイトノイズ様信号を送信して、相互相関関数が伝搬路のインパルス応答h(t)となるようにする方法がある。すなわち、送信信号x(t)の自己相関関数Rx(τ)と送信信号x(t)と受信信号y(t)の相互相関関数Rxy(τ)は、
Rx(τ)=E[x(t)x(t+τ)]=lim(1/T)∫x(t)x(t+τ)dt、(E[x(t)x(t+τ)]は、x(t)x(t+τ)の時間平均)
Rxy(τ)=E[x(t)y(t+τ)]=lim(1/T)∫x(t)y(t+τ)dt
と表され、(1)式から
Rxy(τ)=E[x(t)∫h(τ_1))x(t+τ-r_1)dr_1]
=∫h(τ_1)E[x(t)x(t+τ-r_1)dt]dr_1
=∫h(τ_1)Rx(τ-r_1)dr_1
=h(τ)※Rx(τ)
となる。上の式は、Rx(τ)がδ関数であれば、Rxy(τ)=h(τ)となることを表しているので、自己相関関数がδ関数となるような無相関の既知のホワイトノイズ様信号を送信信号として用いれば、送信信号と受信信号の相互相関関数を求めることによりインパルス応答h(τ)が得られる。
チャネルサウンディングについては、以下を参照
5G mmWave MIMO Channel Sounding(英語pdf)のPage 4
Software Defined Radio based MIMO channel sounding(英語pdf)の2.3 Channel sounding(p9~p11)