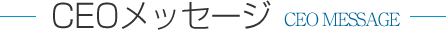高倉健が逝った。彼が主演した「幸せの黄色いハンカチ」を何度観ただろうか。その回数は、映画館の映写技師にも負けないだろう。
アフリカの大使館に在勤していたころ、広報活動の一環で地方の村々によく出かけた。日本文化の紹介の1つとして日本映画を上映するのだが、車に映写機やガソリン発電機などの必要な機材を積み込んで、ドライバーと2人で村々をまわるのである。地方をやみくもに巡回するわけではない。青年海外協力隊員を介したり、村の村長(酋長)や向学心の強い若者たちが大使館にやってきて上映を依頼してくることも多々あった。
地方に出かけるといっても、だとり着くまでが一苦労であった。地図などもなく道なき道を車で向かうのだが、数センチでも車幅を見誤れば崖下へまっしぐらとなる山道。タイヤがすぐに埋まってしまう泥道。明るいうちにたどり着ければラッキーだが、陽が沈むと車のライトだけが頼りとなる。車幅や前方を確かめながら、タイヤを慎重に1回転ずつさせながら進むのである。わたしは、ドライバーに命を預けるのだが、ドライバーは天に命を預けているかのように、亡き母親が子どもの頃に彼に歌ってくれたという子守唄をいつも口ずさんでいた。その子守唄のおかげで、二人っきりの真っ暗闇の車内はいつも穏やかだった。
ある村にいつものように2人で出かけたときだった。何とか日暮れ前に到着し、村人総出の歌や踊りで出迎えを受け、村に伝わる発酵酒を村長と飲み交わした後、広場を利用した天然の上映場でいよいよショータイムとなった。電気が灯ることもなく、村全体が真っ暗闇である。車に積んできた発電機に16ミリフィルムプロジェクターをつなぎ、上映会の始まり始まり~となった。
広場には赤ちゃんを抱っこした母親からお年寄りまで、村人全員が集まった。親近感を感じてくれそうな話題を交えながら日本の農業や日常生活を撮影した広報フィルムを上映して後、日本映画を上映する運びとなった。村人たちの好奇心溢れる目線を感じながら、フィルム走行のスイッチをひねった。車に積んできたスクリーンに「幸せの黄色いハンカチ(Yellow Handkerchief)」と映し出された。
「イエローハンカチーフ」と誰とはなしに、英語を解する数人が大声で字幕を読み上げた。英語をさらに現地語にして、語り始める村人もいた。識字率の低い村落ならではの自然な光景だ。穏やかな時の流れとともに映画が始まった。上映開始後まもなく、字幕を読み上げる声も聞こえなくなった。村人は、映像だけでストーリー展開を理解し始めていたからに違いなかった。派手なアクション映画ではない、淡々と流れる物語。説明を加えずに理解してもらえるのか、心配していた自分が自分で恥ずかしくなった。こっけいな仕草では皆が笑い、悲しい場面では広場の闇が怖くなるほどに静まり返った。
いよいよクライマックスが近づき、どうなることかと誰もが緊張し始めた。殺人を犯した夫が刑期を終え出所してくるのを、はたして妻は待っているのだろうか。待っていれば、黄色いハンカチが玄関か軒下にでも吊り下げられているはずであった。誰もが、息を止めて、その運命の瞬間を待った。
出所した夫は家路の途中で出会った2人の若者に励まされ、家が見える場所までやってきた。はたして、黄色いハンカチは?
2人の若者に促されて見上げた目線の先には?運動会の青空に広がる万国旗のように、これでもかと言わんばかりの数の黄色いハンカチが鯉のぼりの旗竿から延びるロープにくくりつけられ、風にはためいていた。
その瞬間、大歓声がわき上がった。「ウォ~!」。暗闇が一瞬にして、花火でも打ち上がったかのような歓喜の声に包まれた。拍手はいつしか踊りを誘う激しくも軽快なリズムの手拍子へと変わり、若い村人たちは大地を跳ねて踊りだした。1枚ではない無数のハンカチ。説明や終演の言葉など無用であった。
上映を終え機材を片づけ始めると「ありがとう、日本の友よ…日本人もアフリカ人も皆同じ…」と、村長が満面の笑みで語りかけてきた。そのそばから、「イエローハンカチーフは、この村にも皆の心にも幸せを運んできてくれました。本当にありがとう」と子供を連れた母親が目に涙をいっぱいためながら声をかけてきた。
「黄色いハンカチはきっと誰もが持っていると…持っていると誰もが願っていると…」
わたしも、そう答えるのがやっとだった。
翌日、帰路の車内でドライバーがポツリと口にした。「自分の母さんも、きっと喜んでいるよ。自分もこの仕事が一番好きさ」
日本映画をアフリカの奥地で上映しているなんて、日本人は誰も知らないに違いない。かつて、ある新聞記者に、この経験を話したことがあった。「作り話ですよね」と一笑された。黄色いハンカチは、今の日本人にこそ必要なのかもと思った。