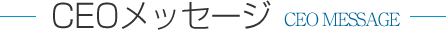父、眠る!
父ちゃん、もう力つきてしまいました。
ただ静かに穏やかな顔して眠っています。
父ちゃん、本当にありがとう!
作年1月某日に届いた姉からのメール。覚悟はしていた。帰心矢の如しだが、駆けつけることが叶わなかった。新型コロナ禍の真っ只中、島には戻れなかった。いや、無理矢理にでも戻ることはできたはずだった。
明日のない世界へ旅立つ父を「おとう!」と呼びかけて見送ることができなかった。きっと「おとう」は病に伏せながらも、”順は必ず顔を見せてくれる”と信じていたに違いなかった。
かつてわたし(順)は、東西冷戦時代の諜報戦の現場に身を晒していたことがあった。その影響で、一線を退いてからも何年間かは身内との接触を完全に封じざるを得なかった。わたし自身を含め、身内へ深刻な危害の及ぶ恐れが多分にあったからだ。それだけは、人生を賭しても防がなければならない。
身内のほとんどが、連絡のつかないわたしの存命をあきらめ、失踪宣告の手続きをすべきとの判断をしていたようだった。その中にあっても「おとう」だけは、”順は必ず生きている””生きて必ず帰ってくる”と頑なに譲らなかったという。
一昨年の春、父は倒れ入院した。食べることの難しくなった父は胃瘻カテーテルを装着した。しかし、病床にありながらも胃ろうを抜去しようとするために、身体拘束帯(ミトン)を着けさせられたようだった。それを聞いたときには、恐怖のような胸の痛みを覚えた。冷戦時代の現場で何度か死を覚悟する局面に陥ったときでさえ、感傷的になることはあっても恐怖を感じることはなかった。
恐怖の中にあっても、穏やかな顔をして眠っていたという父。やはりわたしの「おとう」様だ、と1年を経て改めて、父の人間としての尊厳と偉大さを感じている。物心ついたときからの父の教示は、そこに耐え難き理不尽な厳格さはあったものの、人生を賭してでも守るべき道を示すものだった。