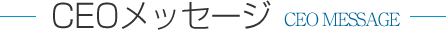“終活(しゅうかつ)”という言葉が使われるようになってきた。言葉に慎重なローカライザーとして、その表現に異様さを感じる。その行為自体は大切なことだ。生前のうちに自身の葬儀や墓などの準備をしておくのは理解できる。多分、自分も年齢を重ねれば”最後を迎えるにあたって”を考え準備するだろう。が”終活”という言葉が”就活”の派生なのか、学生の就職活動と同じレベルで発想されたようで違和感を覚える。
そこには、直接的な表現を避け、敷居を低くくすることで”終活”の商品化が図られる市場が見える。結婚式と同じ発想で”終活”市場もランク付けされていくであろうが、”終活支援”市場にお金が流れることで、セレモニー化による”絆”の形骸化が進む面もある。社会が成熟した証なのか、それとも病んでいるのか。いずれにせよ、”終活”という言葉は使いたくない。
20代の最後のころ、ウィーン滞在中にこういうことがあった。
1日フリーの日があって、午後から街中へ出かけた。航空会社で航空券を購入し、公園でパンとソーセージをほうばりながら読書を楽しんだ。夕闇が迫るころ、そろそろ帰ろうと公園を抜け王宮広場に出ると、テナーサックスのサウンドらしき音が聞こえてきた。ちょっとぎこちないサウンドに足が止まり、目の前のベンチに腰掛けた。学生のころ、吹奏楽をやっていたせいか血が騒いだ。
広場のベンチから音が聞こえてくる商店街の方に目をやると、一見して80歳に手が届きそうな老婦人が歩道に立ってテナーサックスを吹いていた。音楽の都ウィーンとは言え、老婦人とテナーサックスのとりあわせに驚いた。たえだえのサウンドに、メロディーラインさえ掴めない。年齢からして、もはや吹きこなせないのだろう。
わたしは、暇にまかせてサックスから流れ出る音階を頭の中でつむぎ、必死に曲名を探し出そうとしていた。やがて陽は落ち商店街に灯りがともりだしても、その老婦人は何かにとりつかれたかのようにサックスを吹き続けていた。人通りはあるが、誰一人として立ち止まって耳を傾ける者はない。
その老婦人の顔をもっと間近で見たくなり、静かに歩き寄った。かなりの高齢に見える。粗末な服装をまとい、手製のサックスストラップが付いた楽器も相当に古そうだ。「よく、その年齢でサックスを吹いているもんだ」と驚嘆しながら見つめると、彼女は吹くのをやめ、「聞いてくれてありがとう。リクエストは」と、か細い声で話しかけてきた。「エーデルワイス」と答えると、彼女は一瞬知面を見つめ楽器を持ち直した。サックスを吹きはじめた彼女の立ち姿からは威風が漂ってきた。流れ出す旋律は不正確で音は途切れがちに思えたが、音色だけは深重に響き心地良かった。
曲が終わりチップを渡そうとすると彼女がほほ笑んだ。「いいのよ、喜んでもらえれば…」。しわしわの顔の奥まった目は、とても美しかった。チップ受けとして広げてあるボロボロのサックスケースをふと見ると、そこには1枚の硬貨も入っていなかった。「ずっと、サックスを吹いているの?…」と彼女と言葉を交わしていると、通りの向こうからおぼつかない足取りで同年代の男性がトボトボと歩いてきた。
「迎えに来たよ」。「ありがとう」。二人で仲良くサックスをケースにしまうと、男性はケースを右手に持ち、左手で彼女の手をとった。「またネ」「お元気で」と挨拶を交わすと、二人でわたしに笑顔を送り歩きだした。
「もう会えないかも…」わたしの言葉に振り返りながら、笑顔で肩を寄せ合い身体を同じリズムで左右に揺らせながら歩き去る二人の後ろ姿はいつしか、街灯に照らされ揺れる一つの影となっていた。
その影が街かどから消えるまで、掌が痛くなりながらも”Bravo!”と力いっぱいの拍手で見送った。一人しかいない観客の拍手がやむと、街かどは急に寂しくなった。
翌日、ベルリンへと向かう機上から、見えるはずもない老婦人の影をウィーンの街中に探していた。飛行機の窓からウィーンという街に”乾杯”しつつ、老婦人の言葉を思い返していた。「サックスは、最近始めたのさ」。
その老婦人のサウンドは、エーデルワイスのメロディーを奏でてはいなかった。が、その後ろ姿からは、”Brava”と叫びたくなる確かな人生のメロディーがかもしだされていた。
生きるとは、”そういうこと”なのだろう、とウィーンの街角で思った。”終活”という言葉を耳にするたび、街灯に揺れていた老婦人の陰影が浮かぶ。