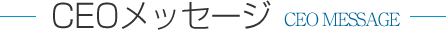硬直した外交政策が膠着を生んでいるのだが、異なる価値観に立てるかどうかで交渉の成否がわかれたりする。そこでは、双方における冷静な分析力が問われるが、この分析力の著しい欠落が外交失墜を招いているようでならない。
かつて、イスラムの世界で勤務していたが、価値観の違う人々が共存していくために、何がわれわれに求められているのかを考えさせられる日々の連続だった。
イスラム教徒最大の宗教祭日にアシューラというのがある。そのアシューラのクライマックスとなる日の宗教行事を街中に観察に出かけたことがあった。その日は、殉教者フセイン(預言者ムハンマドの孫)の命日にあたり、信徒による哀悼の街頭行進が行われる。早朝から、シーア派信徒が太い鎖やむき出しの刀剣、刃物の付いた鎖などを振り回し、自らの胸や背中、頭や額などを激しく傷つけながら街中を集団で練り歩くのである。
わたしは記録を残すため、隠しカメラで行列や街の様子を撮影していたが、周りにいる信徒を刺激することになれば何が起こるか分からないという極度の緊張を強いられた。
血をポタポタとしたたらせ、失血と興奮で気を失い倒れていく信者を街の角々で待機している救急車が次々と運んでいく。その街中の情景に、異なる民族との外交を安直に考えるな、と刃を喉元に突きつけられ悟られているかのような緊迫感を覚えた。
哀悼行進も近年は儀礼的になりつつあるとはいえ、死者も出るというその宗教行事の意味を理解しなければ、イスラムの世界が遠ざかり、外交失策を招くことになる。そこに生きる民、文化、歴史、そこで生きてきた人々を知らずして外交を語れば大きな過ちを犯すことになる。
交渉相手を知ること、理解することは、ビジネスの世界においても重要である。昨今の世情では特に、これらに対する認識が軽んじられているようだ。周りを知ること、隣人を理解しようとすることは、生きるうえでも大切なことのはずだ。
国の外交政策や戦略を立てるには、相当な情報や分析が必要となる。やみくもに号令をかければいいというものではない。分析素養がなければ、相手を知る努力を怠れば、政治家たちの好きな言葉どおり”全身全霊を尽くして”も、”命をかけて”も成果は出せないだろう。
国の外交もビジネス界も似ている。日常を大切に、隣の人に声をかける。同僚を理解する。お客様と話しをする。…。お酒を酌み交わす。各国の人々と交流する。足元を大切に視野を広げる。基本からリスタートしてもいいのでは。きっと、道は開かれる。